 水彩画
水彩画 水彩画展の当番をして感じたこと
那須野が原公園の「綠の相談所」で開催されている「セピアの会水彩画展」の当番になっているので9時から受付や説明などを担当した。受付では観に来てくれる人に氏名や住所を書いていただき、展示品の目録を渡すのだが書いていただけない人もいる。しかし殆ど...
 水彩画
水彩画  水彩画
水彩画  日記
日記 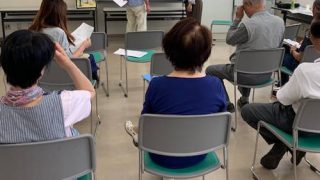 水彩画
水彩画  ウォーキング
ウォーキング  日記
日記  水彩画
水彩画  水彩画
水彩画  水彩画
水彩画  水彩画
水彩画  水彩画
水彩画  水彩画
水彩画  水彩画
水彩画  水彩画
水彩画  日記
日記