 仕事
仕事 会社訪問
アドバイザーとして勤務しているメッキ会社を訪問し5S運動や品質向上対策について幹部や関係者と話し合った。5S運動については各課の計画が月末に提出される予定なので、来月初めに5S事務局と一緒に現場巡回し現状把握してから今年の活動について進め方...
 仕事
仕事  ウォーキング
ウォーキング  日記
日記  日記
日記  里山の再生
里山の再生  ウォーキング
ウォーキング  日記
日記  日記
日記 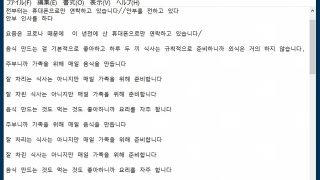 日記
日記  日記
日記  スマホ
スマホ  心臓病
心臓病  心臓病
心臓病  心臓病
心臓病  心臓病
心臓病